その他
緊縛シロウト理性解放実験記 [ 4 ]
上体を縛られ、梁から吊られる。左足を腰と水平に吊る。自分の身体が非日常的ポーズをとることが、なんだかとても可笑しかった。つぎに右足も吊られ、腹部と床が平行になると、そんな暢気は吹き飛んだ。
太腿の痛みか、宙吊りの酔いか、目眩のようなものなのか、未曾有の感覚が身体中を這い回る。動悸、冷汗、耳鳴り、吐き気のようで吐き気でないもの。喜多氏の声も遠のいていく。自分が目を開けているのか、閉じているのかも分からない。これが恐怖なのか、そうでないのかも、分からない。もちろん、時間の感覚もない。視界がみるみる闇に染まっていく。朦朧とする意識の中で、奇妙な感覚が訪れる。腹の真ん中が大きく窪んで丸い穴が空き、そこから大量の水が勢いよく外へと流れ出ていく。水は、この身を構成する「何か」のようで、おおよそ半分は出て行ってしまった。おおよそ、そんなイメージであった。
床に寝かされ、縄を解かれ、視界と呼吸が少しずつ、いつもの自分に戻っていく。よく高熱を出した人が三途の川を見たようなことを言うけれど、ついさっきまでの状態は、それとよく似ているように思う。死を象徴するあの川の前では、恐怖と安堵の狭間に文字通り目を回すのではなかろうか。叫んだり、助けを乞うたり、そんな遑は微塵もないのだ。
多分、私は怖かった。
その怖さは、私の意識が創り出した。
そして、感覚を一つの球とするならば、きっと恐怖は半分だった。残りのもう半分は「思考しない私」つまり無意識の私が見せてくれる世界ではないかと思う。怖れを知って、尚その先に行かんとするのは、その先に在る光を予感できるからだろう。
太腿の痛みか、宙吊りの酔いか、目眩のようなものなのか、未曾有の感覚が身体中を這い回る。動悸、冷汗、耳鳴り、吐き気のようで吐き気でないもの。喜多氏の声も遠のいていく。自分が目を開けているのか、閉じているのかも分からない。これが恐怖なのか、そうでないのかも、分からない。もちろん、時間の感覚もない。視界がみるみる闇に染まっていく。朦朧とする意識の中で、奇妙な感覚が訪れる。腹の真ん中が大きく窪んで丸い穴が空き、そこから大量の水が勢いよく外へと流れ出ていく。水は、この身を構成する「何か」のようで、おおよそ半分は出て行ってしまった。おおよそ、そんなイメージであった。
床に寝かされ、縄を解かれ、視界と呼吸が少しずつ、いつもの自分に戻っていく。よく高熱を出した人が三途の川を見たようなことを言うけれど、ついさっきまでの状態は、それとよく似ているように思う。死を象徴するあの川の前では、恐怖と安堵の狭間に文字通り目を回すのではなかろうか。叫んだり、助けを乞うたり、そんな遑は微塵もないのだ。
多分、私は怖かった。
その怖さは、私の意識が創り出した。
そして、感覚を一つの球とするならば、きっと恐怖は半分だった。残りのもう半分は「思考しない私」つまり無意識の私が見せてくれる世界ではないかと思う。怖れを知って、尚その先に行かんとするのは、その先に在る光を予感できるからだろう。
コメント
この記事に対するコメントはまだありません
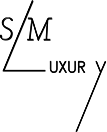






会員登録をすると
コメントを投稿する事ができます
ログインする 会員登録